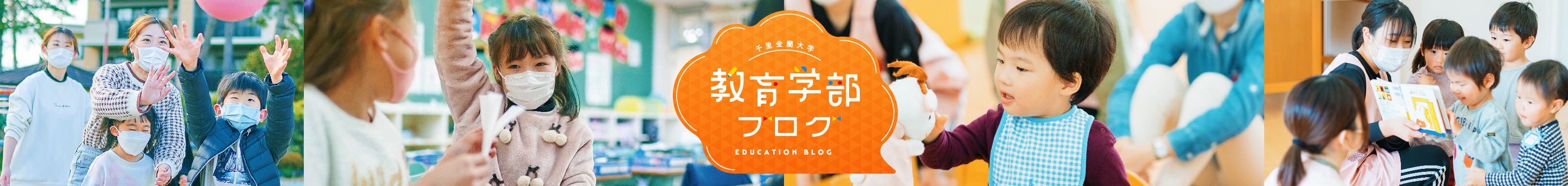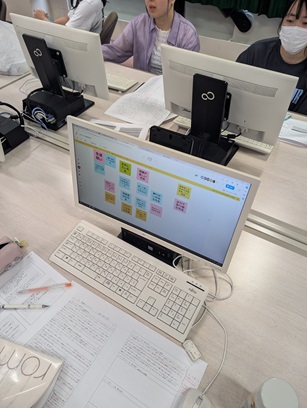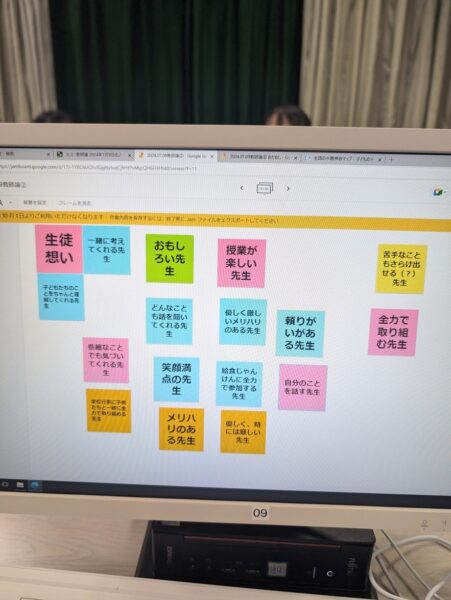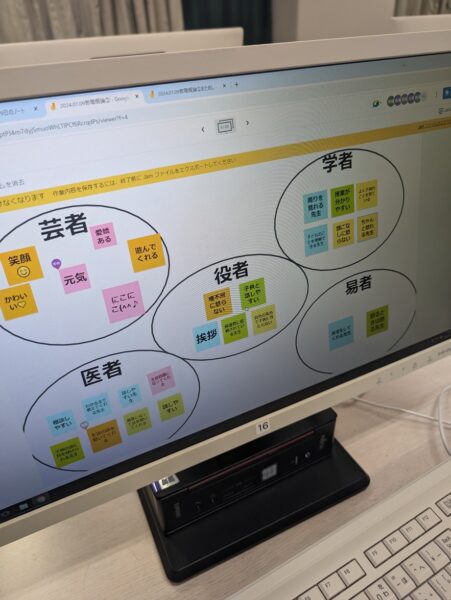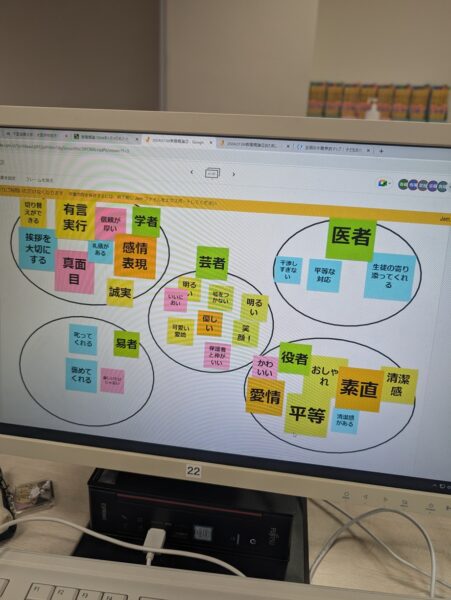講義「教師論」では、「教師の五者論」をテーマにしました。
「教師は五者たれ」という言葉は、教員の業界では、脈々と受け継がれてきた言葉です。
私も初任の頃、先輩の先生から教えていただきましたし、書籍でも読みました。
五者とは、
・学者:教師自身が学び続けなさい
・医者:困っている子どもがいれば、どうすればよりよくなるか見抜き、その「治療」をしなさい ※決して、医学的な見地からのみではありません
・役者:子どもの心に火をつけるために、演じなさい
・易者:「この子はこのままだと……」と、子どもの未来をみられるようになりなさい
※決して、専門的な占いの力をつけなさい、というわけではありません
・芸者:子どもを楽しませなさい
上の5つを指します。
この、昔から教師の業界でいわれてきた「教師は五者たれ」という言葉をもとに、
令和ならではのPCを使って、考えました。
昨今、小学校現場では、1人1台端末環境が整っています。
そのため、学生のみなさんも、数年後に現場に出ると、必ず端末の指導が求められます。
だからこそ、みなさんにパソコンを触ってもらう機会を増やしています。
こうすることで、現場に出たときに
「大学では、あんな使い方をさせていたな」
「似たような思考方法をさせたいな」
「子どもには直接触らせないけど、掲示物の作成としては使えるな」
などと、授業づくりや掲示物づくりのヒントになると考えたからです。
さて、講義ではまず、
「いい先生とはどんな先生か?」
というお題について、全員が意見を出し合いました。
そして、上でお伝えしたように、五者の中身を伝えた上で、
その意見を、五者に沿ってグルーピンクしていきました。
グループによって、意見が異なることにも、気付くことができました。
そしてその上で、自分の強みと弱点を、五者の中から選び、その理由も考えました。
自分の強みと弱点を知っておくことは、教師や保育士、いえ、全ての社会人にとって必要なことです。
今日の授業で考えたことや身に付けたことは、「大学で終わり」ではなく、現場へ持って行ってほしいものです。