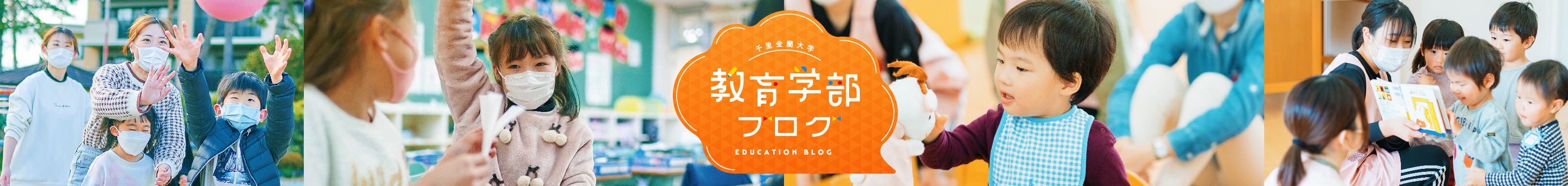前回のブログでは、お絵かきコップの手応えが大きかったことをお伝えしました。
※前回のブログはこちら
今回は、その裏側をお伝えしたいと思います。
最初に、学生と確認したことは、
単にお絵かきの手順を説明するだけでは、児童に「やらされ感」が出てしまうため、
そうならぬようにしよう、ということでした。
そこで、「やらされ感」を払拭するためにどうすればいいか、皆で知恵を出し合いました。
結果、
・千里ニュータウンの歴史を知ってもらうこと
・千里キャンドルロードにこめられた願いも伝えること
を盛り込んでいこう、という方向になりました。
子どもたちに歴史や願いを伝えるためには、まず、自分たちが知らなければなりません。
そこで、以前にゲストでお越しくださった方のお話を思い出したり
(そのときの様子はこちら)、
地域の方が立ち上げているHPを拝見したりした上で、
パワーポイントの作成に取り掛かりました。
また、パワーポイント作成の折には
・小学校では、モニターの大きさにもよるが、フォントの大きさが44より小さくならぬこと
・書体「メイリオ」がわかりやすいこと
・文字ばかりのスライドは、あまりよくないこと
・写真には、キャプションがあると、伝わりやすいこと
など、長年の小学校現場経験のある教員(私ですが……)から、
小学校現場ならではのアドバイスもなされました。
こういった下準備があってこそ、児童の前に立ったときに大きな手応えが得られるのだと思います。
また、いくら丹念に準備をしたとて、児童の反応は、こちらの想定を上回ってくることが、よくあります。
そのため、その場で咄嗟に、臨機応変に立ち回る必要もあります。
準備も大切ですが、臨機応変に対応できることも、同じくらい大切です。
今回の経験を糧に、
残りの大学生活も、そして社会人になっても、
準備を大事にしつつ、それと同時に、臨機応変に対応できる人物になってほしいと思いました。
教育ゼミでは今後、藤白台小学校を訪れておこなう「さんすうきょうしつ」の企画・準備に加え、
卒業論文に向けての内容も追加されます。
卒業論文は、答えが定まっていない1つのテーマについて、何か月間も考え続けます。
このような経験が初めて、という人も多いでしょう。
確かに骨の折れる、たいへんなことではありますが、自分の頭の中を言語化する、めったにない機会でもあります。
また、自分の頭の中を言語化することは、小学校の先生になっても、社会人になっても必要とされることです。
教員採用試験対策も、卒業論文も、日々の講義も、そしてプライベートも、楽しみながら取り組んでくれることを願っています。