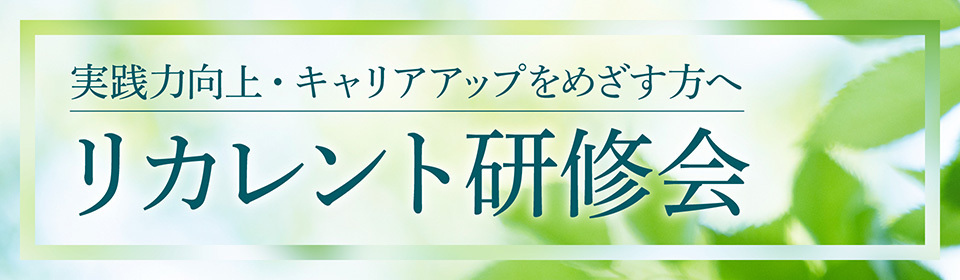助産師教育課程
「助産師のアイデンティティを育み、母子とその家族に必要なケアが行える助産実践能力の修得をめざす、
学士課程初の助産師教育課程 第三者評価「適格」認定施設です。(一般財団法人 日本助産評価機構 大学(学士課程)第一号)

助産師とは
助産師は英語ではmidwifeと表され、これはwith woman(女性とともにいる人)という意味です。
日本においては、「厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」(保健師助産師看護師法保助看法第3条)とされています。しかし、国際助産師連盟(ICM:International Confederation of Midwives)の定義では、「助産師は、女性の妊娠、出産、産褥の各期を通じて、サポート、ケア及び助言を行い、助産師の責任において出産を円滑に進め、新生児及び乳児のケアを提供するために、女性とパートナーシップを持って活動する。これには、予防的対応、正常出産をより生理的な状態として推進すること、促すこと、母子の合併症の発見、医療あるいはその他の適切な支援を利用することと救急処置の実施が含まれる。助産師は、女性のためだけではなく、家族及び地域に対しても健康に関する相談と教育に重要な役割を持っている。この業務は、産前教育、親になる準備を含み、さらに、女性の健康、性と生殖に関する健康、育児におよぶ。助産師は、家庭、地域(助産所を含む)、病院、診療所、ヘルスユニットと様々な場で実践することができる。」とされ、助産師の仕事はより具体的に、また、女性とともに歩むことが明確に打ち出されています。
このように、助産師の仕事とは、女性とその家族に寄りそい、その一生を通じて健康支援をしていく専門家です。
特色
- 1. 実践を想定した授業
- 事例を使った演習を多く取り入れ、状況に合わせた実践的な思考と技術が身に付くよう工夫しています。例えば、妊娠期や産褥期の保健指導ロールプレイでは、本学で養成したSP(Simulated Patient=模擬患者)に妊婦・褥婦役になっていただいています。初対面の妊婦・褥婦とコミュニケーションを取りながら必要な情報を得てアセスメントし、個別性のある保健指導ができる能力を養っています。さらに、そのロールプレイ場面は、SPからのリフレクションをいただき、学生・教員間で講評して学びを深めています。
この他にも、助産師として活躍する実践家を招いて、母乳育児支援、フリースタイル出産、助産に活かす東洋医学、新生児蘇生法(NCPR Aコースの資格取得)、助産所の院長による管理業務などの授業や演習をしています。 - 2. 少人数での教育
- 1学年上限7名での教育を行っています。講義は質問しやすく、個々の理解度に合わせて進められています。また、演習・実習では1~3名の学生に1名の担当教員がつき、きめ細やかな指導を行っています。
-
3.
教員と学生、4年生と
3年生の双方向的教育 - 講義形式の授業ばかりでなく、3~4名のグループ編成でディスカッションを行ったり、ひとつのテーマでディベートを行ったりと、論理的思考や自分の意見をもって他者に伝える力を養っています。演習でもグループで課題に取り組む機会を増やし、助産師に必要な主体性、コミュニケーション力、協調性などを培っています。
4年生の継続事例発表会に3年生も参加したり、オープンキャンパスの体験プログラムをいっしょに運営したりと、学年を越えた交流ができます。 - 4. 充実した実習内容
- 分娩介助を行う実習病院では、病院の臨床指導者と大学の教員との連携を密にして、学生の実習をサポートしています。産後入院中のケアを学ぶ産褥実習や、ひとりの女性の妊娠期から1か月健診までを受け持たせていただく継続事例実習も行っています。 継続事例実習は、助産所で行っています。妊娠期から密に関わることで、対象との信頼関係や個別性を大切にしたケアの重要性なども学んでいきます。
教育目標
- 医療人としてのプロフェッショナルな意識を基盤とし、助産師のアイデンティティを育成する
- 母子とその家族に対して、豊かな人間性と倫理的感応力に基づいた支援が行える能力を育成する
- 正常なマタニティサイクルにおいて助産が行えるための、基本的な助産診断技術を育成する
- 女性の一生涯を通じ、quality of lifeを高める基本的支援が行える能力を育成する
- 社会の発展のために助産師として積極的に貢献しようとする意志を養う
3つのポリシー
- アドミッションポリシー
-
- 助産師を志す明確な意志を有している人。
- 助産学を学ぶ上で必要な基礎学力と、看護学の基本的知識を備えている人。
- 協調性があり、他者とコミュニケーションがとれる人。
- 豊かな人間性と、看護を基盤とした倫理観を有している人。
- 社会に対し関心をもち、地域の母子保健や周産期医療に貢献しようと意欲のある人。
- カリキュラムポリシー
-
- 助産学に関する基本的な知識や周産期医学の専門的知識を基盤に、助産実践力を育成するための科目を設けている。
- 基盤となる助産学では助産の概念や意義、助産師の倫理や社会における責務を学び、自らの思考過程の核に助産というパラダイムを構築させる。
- 助産学実習では、自然性を尊重できる感性が養え、妊娠から分娩、産褥までに必要な助産診断、助産技術が統合して学べるような教育内容を設ける。
- 助産師として地域の保健・医療に貢献する意欲を高めるような教育内容を設ける。
- ディプロマポリシー
-
- 助産師としての自己の将来ビジョンを描くことができる。
- 対象となる女性や生まれくる子ども、およびその家族を尊重し、信頼関係を築き、そのニーズに倫理的に応答できる。
- 妊娠~産褥までのマタニティサイクルを包括的に捉え、女性が母親になること、家族を形成することへの必要な助産ケアが提供できる。
- リプロダクティブ・ヘルス/ライツの視点から、女性の一生涯を通じ、quality of lifeを高める基本的な支援ができる。
- 周産期医療における助産師の専門性に誇りをもち、自律した医療人として責任と役割を果たそうとする姿勢が身についている。
- 地域における助産師活動に積極的な関心をもち、母子保健の向上のために貢献しようとする姿勢が身についている。
カリキュラム(2021年度以前の入学生)
[人数]7名(上限)
2年次後期に選抜試験を実施します。選考は、筆記試験(母性保健医療学演習、母性看護対象論)、面接、2年次後期までに履修したすべての科目の成績の結果を総合して審査します。
| 科目名 | 配当年次・ 学期 |
単位数 |
|---|---|---|
| 周産期医学Ⅰ | 3年前期 | 2 |
| 周産期医学Ⅱ | 3年前期 | 2 |
| 助産論演習 | 2年後期 | 1 |
| 地域母子保健 | 3年後期 | 1 |
| 助産管理論 | 4年前期 | 2 |
| 助産診断技術学Ⅰ | 3年後期 | 2 |
| 助産診断技術学Ⅱ | 3年後期 | 2 |
| 助産診断技術学Ⅲ | 4年前期 | 2 |
| 助産診断技術学演習 | 4年前期 | 3 |
| 助産学実習 | 4年後期 | 11 |
カリキュラム(2022年度以降の入学生)
[人数]7名(上限)
2年次後期に選抜試験を実施します。選考は、筆記試験(母性保健医療学演習、母性看護対象論)、面接、2年次後期までに履修したすべての科目の成績の結果を総合して審査します。
| 科目名 | 配当年次・ 学期 |
単位数 |
|---|---|---|
| 周産期医学Ⅰ | 3年前期 | 2 |
| 周産期医学Ⅱ | 3年前期 | 2 |
| 助産学概論 | 2年後期 | 2 |
| 地域母子保健 | 3年後期 | 2 |
| 助産診断技術学Ⅰ | 3年後期 | 2 |
| 助産診断技術学Ⅱ | 3年後期 | 2 |
| 助産診断技術学Ⅲ | 4年前期 | 2 |
| 助産管理論 | 4年前期 | 2 |
| 助産診断技術学演習 | 4年前期 | 4 |
| 助産学実習 | 4年後期 | 11 |